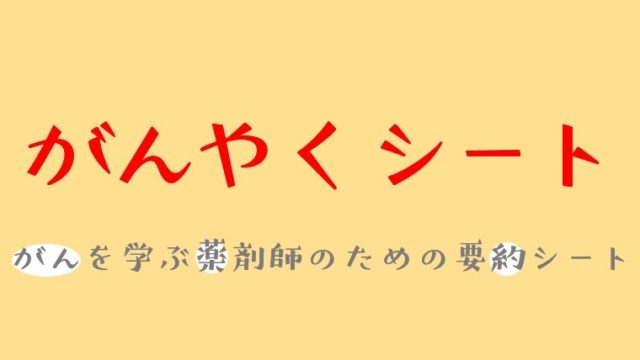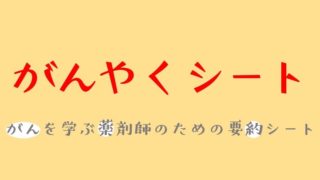年間1万人ほどであり、肺・大腸・胃・乳がんなどと言ったメジャー癌と比べるとちょっとマイナーなところはあるかもしれませんね。
筋層非浸潤の膀胱がん(CIS)は膀胱注入療法が大事!
まず、TUR-Bt(経尿道的膀胱腫瘍切除術)という手術があります。
尿道に棒を差し込んで、中から膀胱壁の腫瘍を切り取るという手術だそうです。
私も術後の患者さんを見ることがありますが、尿カテって痛そうです…。
で、その後に膀胱の中に薬液を注入して1,2時間浸す。これが膀胱注入療法ですね。
使われる薬剤は
- マイトマイシン
- アドリアマイシン
などが挙げられますが、薬剤間に差はないとされています。
術後6時間以内に行う事が多いですね。
膀胱注入療法では一般的な全身化学療法とは違い、全身に抗がん剤が回るわけではないため、いわゆる細胞毒性に伴うような副作用はほとんど起こりません。
脱毛もないし、吐き気もない。
膀胱刺激症状や、血尿、尿の着色は起こりえますね。でも1,2日で消失することがほとんどです。
高リスクの筋層非浸潤膀胱がんに対してはBCGが膀胱注入されています。これは術後すぐではなく、週1回、6〜8週での投与が一般的です。
副作用は意外と多く、一番多いのは膀胱刺激症状、ついで血尿・排尿障害はよく目にします。これらも1,2日で消失することが多いのですが、注意が必要なのは38〜39℃を超えるような発熱、全身倦怠感、関節痛、鼠径リンパ浮腫、肺炎や目のかすみなど。
極稀ですが、こういう怖い副作用も起こりえます。
術前化学療法はM-VACがガイドライン上は推奨されているが…
まず、筋層浸潤性膀胱がんの標準治療は膀胱全摘であり、手術単独での5年生存率は50%といわれています。
「T3以上の場合、これに術前化学療法。
全摘してみてT2以上だった場合、術後補助化学療法をかぶせる。」
というのが一定の方向性のように思います。(当院医師、H30がん専門薬剤師集中講義内容などから…)
ガイドラインにもここらへんについてはああしろ、こうしろという明確な記載はありません。
で、術前化学療法の利点としては
- 複数のランダム化比較試験からシスプラチン含有レジメンの生存期間延長が示されている
- 化学療法の反応性をチェックできる
- 適切な化学療法を遅延なくやりやすい
- 術後よりも化学療法の忍容性が高い
- 微小転移に対する効果が期待できる
- 化学療法が著効すれば臓器温存が出来るかもしれない
欠点としては
- 病理診断に影響することがある
- 効かなかった場合、根治治療を逸する可能性がある
- 過剰治療のおそれもある
といわれています。
使用レジメンについてですが、元々M-VAC療法(メトトレキサート、ビンブラスチン、アドリアマイシン、シスプラチン)のレジメンが基本としてありました。
膀胱がんガイドライン2015ではまだこの記載ですが、世の中的にはGC療法を使用するほうが多いようで、臨床腫瘍学会、がん治療学会等でも正直M-VACを優先して使うという話はあまり見かけず、成書でもGC療法が既に一般化しているように思います。
既報を見てもM-VACは患者も疲弊してしまう割にOSには寄与しない、GCは完遂率も高い。という報告が多いです。
次の改訂でGCも記載されるのかなー、なんて思っています。
転移がん・再発がんはGC療法が一般的
こちらもM-VACが90年代の主役だったようです。
ですがとにかく副作用が強く、
Grade4 好中球減少:65.2%
Grade2-3 口内炎:49%
Grade3-4 悪心嘔吐:20.8%
治療関連死 最大3%
というちょっと今では考えられないレベルの頻度です。
で、効果は同等、副作用は少ない!という売り込みでこちらもGC療法が一般的になってきたわけですね。
| 5年生存率 | 無増悪生存期間(PFS) | 全生存期間(OS) | |
| MVAC療法 | 15.3% | 8.3ヶ月 | 15.2ヶ月 |
| GC療法 | 13.0% | 7.7ヶ月 | 14.0ヶ月 |
Long-term survival results of a randomized trial comparing gemcitabine plus cisplatin, with methotrexate, vinblastine, doxorubicin, plus cisplatin … – PubMed – NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16034041
このGC療法は4週サイクルで
day1 GEM
day2 CDDP
day8 GEM
day15 GEM
という内容なんですが、day15が大体骨髄抑制でSkipになるっていう理由でday15を削除して3週回しにしたレジメンのほうが最終的なRDIが高くなるという報告もあり、やっている施設もあるようです。(うちはやってます)
他にも腎機能不良例に対してシスプラチンの代わりにカルボプラチンを使用するというレジメンも試みられているようですね。
今まではこのあとの2次治療として、GC+PやGEM+PTX、PTX+IFM+Nedaなどのパクリタキセル含有レジメンが行われていましたが、これも施設間により差があるようです。
そんななか明確な2次治療として立ち位置を確保したのはペンブロリズマブでした。(2015年ガイドラインには当然載ってませんが、今後載るでしょう)
ペンブロリズマブは3週ごとの投与ですが、1回につき73万円の薬剤費がかかるという超高額薬品です。
KEYNOTE-045試験はプラチナ抵抗性の尿路上皮がんを対象に
ペンブロリズマブ vs タキサン(vinflunineという日本未承認薬も含む)という試験でした。
| 1年生存率 | 全生存期間(OS) | |
| ペンブロリズマブ | 43.9% | 10.3ヶ月 |
| 化学療法 | 30.7% | 7.4ヶ月 |
カプランマイヤーがやっぱり3ヶ月でクロスしてたり、irAEは怖かったりもしますが、成果としてはよい成績だったといえるのではないでしょうか。
こうして、尿路上皮がんは現時点ではこのような治療を行うようになっているというわけです。
ちょいマイナー癌であるということもあり、そこまでエビデンスがガッチリしてないかもしれませんが、これにて終了でございます。
膀胱がんガイドライン2015年版:日本泌尿器科学会http://www.urol.or.jp/info/guideline/data/01_bladder_cancer_2015.pdf
不明点・ツッコミどころ等あればご指摘くださいませ!
↓クリックおねがいします!